冷蔵庫を買うときは「高価な買い物だから失敗したくない」と悩む人が多いのではないでしょうか。
そんな人のために本記事では、冷蔵庫の選び方や「買ってよかった」と評価されている冷蔵庫とその理由を紹介しています。
さらに「これは買わないほうがいい」という冷蔵庫の特徴も解説します。
買ってから後悔しないように必須のポイントを押さえ、最適な冷蔵庫を選びましょう。
買ってよかったと思える冷蔵庫の選び方は?
「買ってよかった」と思える冷蔵庫の選び方を具体的に解説します。
扉の開き方で選ぶ

冷蔵庫の扉の開き方には4種類あります。
- 右開き
- 左開き
- 両開き(ドアが1つで、左右どちらからも開けられる)
- 観音開き(ドアが2つで、左右にガバっと開ける)
扉の開き方を考えず買うと「部屋に置いたときに扉が開けられない」なんてことになりかねません。
どこに設置するのか、家具や壁に当たらない開き方はどれか、購入前に確認しておきましょう。
容量で選ぶ

冷蔵庫を購入するときは、自分の生活スタイルに合った容量かを確認しましょう。
容量の目安がわからない人は、以下の計算式に当てはめて考えてみてください。
冷蔵庫の容量 = 70L x 家族の人数 + 100L(常備品容量)+ 70L(予備容量)
つまり、4人家族の場合は「70L×4+100L+70=450L」という計算になります。
独自の機能で選ぶ

冷蔵庫を販売しているメーカーごとに独自の機能があります。
たとえば東芝の冷蔵庫なら、野菜に適した「低温で高湿度の環境」を実現してくれる「摘みたて野菜室」が有名です。
また、パナソニックの冷蔵庫には、従来のチルド室より3℃低い温度で、冷凍せずに新鮮さを保てる「微凍結パーシャル」があります。
どういった機能が欲しいかで冷蔵庫を選ぶのも、おすすめの選び方です。
野菜室や冷凍室の位置で選ぶ

冷蔵庫の種類やメーカーによって、真ん中の部屋が野菜室または冷凍庫と異なるため、便利さで選びましょう。
自炊する頻度が高く、野菜をよく利用する人は真ん中が野菜室の冷蔵庫が向いています。
毎日自炊をするわけではなく、冷凍食品や作り置きを多く利用する人は冷凍庫が真ん中の冷蔵庫がおすすめです。
冷蔵庫は日々利用する生活用品なので、使い勝手のよい商品を選びましょう。
買って後悔しない冷蔵庫とは?
ここでは、冷蔵庫を選ぶときの疑問に回答していきます。
買ってよかった冷蔵庫のおすすめメーカーは?
買ってよかった冷蔵庫のおすすめメーカーは以下の5つです。
野菜室をよく使うなら「東芝」

東芝の冷蔵庫といえば、野菜室の性能が高い「ベジータ」シリーズが有名です。
使いやすいように野菜室が中段にあったり、鮮度を保つ設定が簡単にできたり、野菜を美味しく食べたい人におすすめです。
刺身やお肉の鮮度を保ちたいなら「SHARP(シャープ)」

シャープの冷蔵庫は、シャープの独自技術「プラズマクラスター」を搭載したモデルが人気です。
プラズマクラスターは空気を浄化し、カビやウイルスの発生を抑える機能です。
プラズマクラスターをチルド室に搭載した「プラズマクラスターうるおいチルド」の機種なら、チルド室を無風状態にできるので、刺身やお肉が乾燥せず鮮度を保てます。
冷蔵庫の匂いを抑えたいなら「Panasonic(パナソニック)」

パナソニックの冷蔵庫は、たくさんの機能を搭載しているのが特徴。
食材の美味しさを保つ「はやうま冷凍」、匂いを抑える「ナノイー」などが代表的です。
「冷蔵庫を開けたときの匂いがイヤだった」という人はナノイー搭載の機種を選んでみましょう。
チルド室を活用したいなら「日立」

日立の冷蔵庫は、チルド室を最大限活用したい人におすすめです。
おすすめ機能は、冷蔵室全体をチルド室に切り替えられる「まるごとチルド」です。
冷蔵庫内の湿度を80%にキープできるので、ケーキやサラダをラップせずに保存できます。
電気代を節約したいなら「三菱」

三菱の冷蔵庫は「全室独立 おまかせA.I.」を搭載したモデルが人気です。
「全室独立 おまかせA.I.」は全室に扉開閉センサーと温度センサーがついており、冷蔵庫内の温度を無駄なく調整できます。
タッチパネルで「部屋別おまかせエコ」に設定するだけでAIが生活パターンを学習し、自動で冷却したり、エコ運転をしてくれたりします。
一人暮らしにおすすめの冷蔵庫は?
一人暮らしの冷蔵庫は、100~200Lがおすすめです。
自炊を全くしない人であれば、100L程度のサイズでもストレスなく生活できます。
週2~3日の頻度で自炊をする場合は、食材を多めに入れられる200Lの冷蔵庫を選びましょう。
100〜200Lで一人暮らしにおすすめの冷蔵庫は以下の2つです。
三菱「MR-P17H」

三菱の「MR-P17H」は、容量が168Lであり、チルド室がついている冷蔵庫です。
冷蔵庫の棚が4段になっており、収納がしやすいため、よく自炊をする人におすすめです。
ドアポケットも大容量であり、高さ調節もできるため、ペットボトルや調味料が入れやすくなっています。
ドアは右開きなので、右側に壁がある家だと使い勝手がいいでしょう。
パナソニック「NR-B17HW」
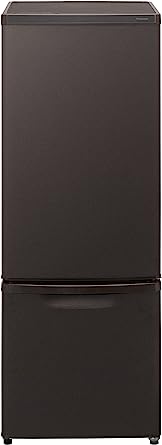
パナソニック「NR-B17HW」は本体の高さが1293mmと低いにもかかわらず、容量が168Lの冷蔵庫です。
冷凍室の容量が34Lと大きく、冷凍食品や作り置きのおかずが保存しやすくなっています。
トップテーブルは耐熱温度100℃であり、電子レンジを置けるため、一人暮らしにもぴったりです。
ドアは右開きなので、右側に壁があると使いやすいでしょう。
二人暮らしにちょうどいいおすすめの冷蔵庫は?
二人暮らしの冷蔵庫を選ぶなら、200〜300Lがおすすめです。
先ほどの計算式に当てはめると以下のようになります。
二人暮らしの容量 = 70L x 2 + 100L(常備品容量)+ 70L(予備容量)= 310L
「買い置きを増やしたい」や「氷をいっぱい使いたい」など、ライフスタイルに合う機能があるかで選ぶのもいいでしょう。
200〜300Lで二人暮らしにおすすめの冷蔵庫は以下の2つです。
三菱「MR-CX37H」
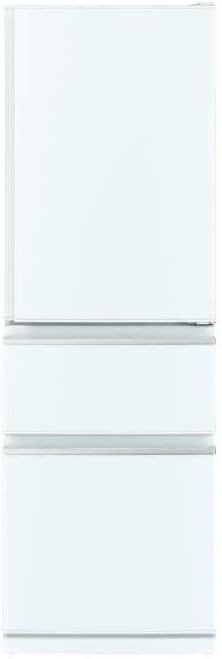
「MR-CX37H」は容量365L、野菜室が真ん中に備え付けられている三菱の冷蔵庫です。
冷蔵庫内の棚の間隔が広く、入れるものによって自由にレイアウトできます。
自動製氷機付きなので、毎日自分で氷を作る必要がないのも人気のポイントです。
ドアは右開きなので、右側に壁があると食材が取り出しやすいです。
ハイセンス「HR-B2501」

「HR-B2501」は容量が250Lとコンパクトで大容量なので、狭いキッチンでも利用しやすいハイセンスの冷蔵庫です。
「お金をあまりかけたくない」「最低限の機能があればいい」という人におすすめです。
ドアは右開きなので、壁が右側だと使いやすいでしょう。
4人家族でも満足できる冷蔵庫は?
4人家族の冷蔵庫を選ぶなら、400〜500Lがおすすめです。
先ほどの計算式に、4人家族を当てはめると以下になります。
4人家族の容量 = 70L x 4 + 100L(常備品容量)+ 70L(予備容量)= 450L
家事に便利な機能やライフスタイルに合わせた性能があるか、確認してから購入しましょう。
4人家族におすすめの冷蔵庫は以下です。
三菱「MR-MZ49J」

「MR-MZ49J」容量462L、「切れちゃう瞬冷凍」を搭載している三菱の冷蔵庫です。
「切れちゃう瞬冷凍」とは、食材を「−7℃」で凍らすことで、解凍しなくても包丁で切れる機能です。
一般的な冷凍庫は「−18℃」ですが、「切れちゃう瞬冷凍」は芯から均一に凍らすことにより「−7℃」でも冷凍できます。
観音開きなので、食材を取り出しやすいです。
Panasonic(パナソニック)「NR-E419EX」

「NR-E419EX」は容量406L、「ナノイー」を搭載したパナソニックの冷蔵庫です。
消臭機能のある「ナノイー」が冷蔵庫内全体に行き渡るので、菌やウイルスが増えるのを抑え、常に清潔にしてくれます。
また「微凍結パーシャル」といって、「-3℃」で食品の表面を凍らせ、腐るのを防ぎ、作り置きを新鮮に保てます。
右開きなので、右側に壁がある配置だと使いやすいです
冷凍庫が大きい冷蔵庫は?
冷凍庫が大きいと、冷凍食品や作り置きの食材をたくさん保存できて便利です。
冷凍庫が大きい冷蔵庫のおすすめは以下の2つです。
シャープ「SJ-PD28G」
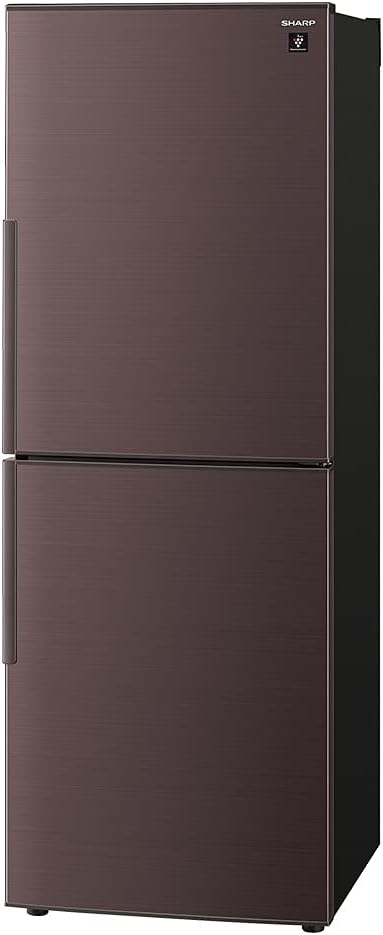
「SJ-PD28G」は容量280L、プラズマクラスターを内蔵したシャープの冷蔵庫です。
大容量冷凍室「メガフリーザー」が搭載されており、125Lの収納を実現しています。
容量277Lのハイセンス「HR-B2302」は冷凍室が53Lなので、メガフリーザーは約2.3倍の収納力があります。
右開きなので、壁が右側のほうがいいでしょう。
東芝「GR-V550FH」

容量551Lの東芝「GR-V550FH」も、冷凍庫が大きい冷蔵庫です。
冷凍室は148Lの容量があり、上段と下段に分かれているので、入れるものによって使い分けられます。
他にも野菜室が真ん中にあったり、冷蔵庫のドアが自動で開いたり機能が満載です。
観音開きなので食材が取り出しやすく、自炊が多い人におすすめです。
買ってはいけない冷蔵庫の特徴とその理由
買ってはいけない冷蔵庫の特徴は以下です。
- 生活スタイルにあった容量ではない
- ドアの開き方が部屋に合っていない
- 霜取り機能がない
- 冷凍庫が小さい
- 消費電力が高い
「作り置きが多い」「外食が多い」など、生活スタイルに合った容量の冷蔵庫を買わなくてはいけません。
「大は小を兼ねる」ともいいますが、大きくなるほどスペースや金額も必要なので、冷蔵庫の場合は適切な大きさを選ぶのがいいでしょう。
ドアには「右開き」「左開き」「観音開き」「両開き」の4種類があります。
冷蔵庫のドアを開けたときに家具や壁に接触せず全開できるか、購入前に確認しておきましょう。
霜取り機能のない冷蔵庫だと、定期的に掃除しなければ分厚い霜がついてしまいます。
霜がついたままでは正常に稼働しないため、手入れの楽さを考えるなら霜取り機能がついた冷蔵庫を選びましょう。
また、冷蔵庫によって冷凍庫のサイズはさまざまあるため、利用頻度に適していないと不便を感じてしまいます。
作り置きや冷凍食品を利用する頻度が多い人は、大きい冷凍庫が搭載されている冷蔵庫を選びましょう。
中古や古いモデルを購入する場合、消費電力が高くなり電気代が高騰する可能性もあります。
冷蔵庫を購入する際には消費電力を確認することに加え、省エネ性能が優れているかを確認しましょう。
なお「買ってはいけない冷蔵庫の特徴」は、こちらの記事で解説しているのでぜひ参考にしてください。

買ってよかった冷蔵庫とその理由
ここからは、買ってよかった冷蔵庫をユーザーの感想と合わせて紹介します。
| 商品名 | 価格(税込み) | 容量 | 機能 | ドアタイプ | 寸法 |
|---|---|---|---|---|---|
Panasonic(パナソニック)「NR-F609WPX-H」 | 350,000円 | 600L | ・うまもり保存 ・AIクーリング ・停電そなえモード | 観音開き | 685 x 745 x 1,828mm |
日立 「R-HW54S」 | 208,000円 | 540L | ・うちまるごとチルド ・特鮮氷温ルーム | 両開き | 650 x 701 x 1,833mm |
アイリスオーヤマ 「IRSD-14A-W」 | 29,980円 | 142L | ・ボトムフリーザー | 右開き | 500 x 549 x 1,215mm |
三菱「MR-WZ55J」 | 263,780円 | 547L | ・切れちゃう瞬冷凍 ・全室独立おまかせA.I ・ひろびろ氷点下ストッカー | 観音開き | 699 x 650 x 1,833mm |
Panasonic(パナソニック)「NR-F609WPX-H」

ナノイーが搭載され、冷蔵庫内の菌やウイルスを除去する、常に清潔な冷蔵庫が「NR-F609WPX-H」です。
購入者からは「省エネ性能が素晴らしく電気代が安くて助かっている」との声がありました。
女性 / 40代中盤
作り置きおかずが好きでよく冷凍します。霜つきや乾燥を抑えて、冷凍保存中の約1ヶ月間おいしさを守ってくれる「うまもり保存」という機能がすごく便利で気に入っています。省エネ性能が素晴らしく電気代が安くて助かっています。
電気代を抑えるためにも省エネ性能を確認することも、冷蔵庫選びのコツのひとつです。
日立 「R-HW54S」

「R-HW54S」は冷凍庫が真ん中にあり、整理しやすい3段ケースになっているのが特徴です。
購入者からは「コンパクトなのに大容量でありがたい」との声がありました。
女性 / 30代後半
以前使用していた冷蔵庫は400l程で、こちらの冷蔵庫とほぼサイズは同じなのに540lと大量用なところ。冷凍庫も3段になっていてたくさん入るのでありがたいです。 以前使用していた冷蔵庫は400l程で、こちらの冷蔵庫とほぼサイズは同じなのに540lと大量用なところ。冷凍庫も3段になっていてたくさん入るのでありがたいです。
冷凍庫に多くの食材が入るので、作り置きや買いだめをする人にピッタリです。
アイリスオーヤマ 「IRSD-14A-W」

「IRSD-14A-W」一人暮らしにピッタリのサイズ感(容量142L)の冷蔵庫です。
高さが121.5cmで上部が熱に強い作りなので、レンジを置いたりトースターを置いたり、スペースの有効活用ができます。
購入者からは「お手頃価格で使いやすい」との声がありました。
男性 / 40代後半
コスパが良く自分が探した中では一番お手頃価格でした。冷凍室が3段の引き出しタイプで出し入れがしやすいです。
冷凍庫も52L収納できるので、冷凍食品や作り置きも十分収納できるでしょう。
三菱「MR-WZ55J」

「MR-WZ55J」は容量462Lで4人以上の世帯におすすめの冷蔵庫です。
観音開きタイプなので中が見やすく、食品を取り出しやすいです。
購入者からは「切れちゃう瞬冷凍が使いやすい」との声がありました。
男性 / -(大阪府)
結婚して新居に引っ越すに当たって、冷蔵庫を新調しました。決め手は462Lという大きさと、「切れちゃう瞬冷凍」という機能です。冷凍食品を完全に凍らさずに保存できるので、解凍不要ですぐ調理に使えるのがとても便利です。
切れちゃう瞬冷凍により解凍せず調理ができるので、家事を楽しみたい人にはピッタリです。
まとめ
「買ってよかった」と思える冷蔵庫を選ぶためには、以下の3つを重視しましょう。
- 扉の開き方で選ぶ
- 容量で選ぶ
- 独自の機能で選ぶ
- 野菜室や冷凍室の位置で選ぶ
本記事で紹介している「買ってよかった冷蔵庫とその理由」を参考に、自分にぴったりな製品を見つけてくださいね。


















コメント